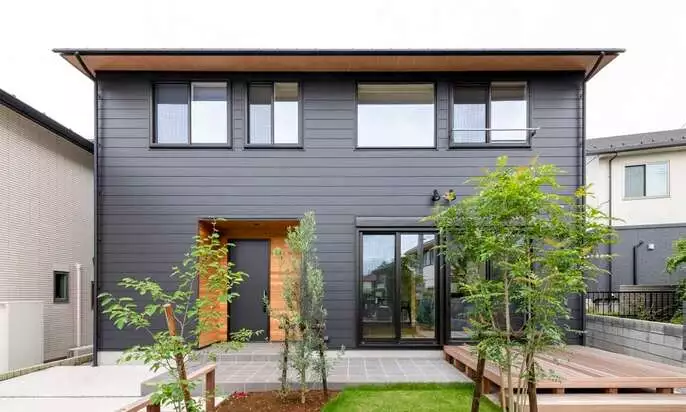なぜ換気が必要なのか

空気を汚す主な原因は3つ
空気を汚す原因は主に3つあると考えられています。まず、人が呼吸するなどして発生する二酸化炭素や湿気。次に、建材や家具、日用品などから出るホルムアルデヒドなどの有害な化学物質。最後は、ストーブやファンヒーターなどの暖房器具から出る排気ガスです。
シックハウス症候群の対策で換気システムは義務化されている
室内の建材や家具などからは、さまざまな化学物質が発生します。空気中の大気が滞留し、化学物質の濃度が高くなれば、時にのどの痛みや頭痛、吐き気などの症状をもたらすことがあります。これが「シックハウス症候群」です。現在の建築基準法では、シックハウス症候群対策のため、原則としてすべての住宅(低気密の住宅を除き)化学物質の発生量が少ない建材を使用すること、また機械による換気システムを設置することが義務づけられています。たとえば、一般住宅の場合だと、1時間に0.5回以上の換気が必要です。つまり2時間で室内のすべての空気を入れ替える換気システムを導入しなければいけません。
どのような換気方法があるのか
一口に換気と言ってもその方法や種類はさまざまです。多くの方が換気と聞いてイメージするのは、窓を開けて空気を取り込んだり、キッチンの換気扇を回したりすることではないでしょうか。それらはそれぞれ自然換気、機械換気に分類されます。ここでは換気の方法についてこの2通りのやり方を詳しく確認していきましょう。

自然換気
自然換気は名前の通り、風圧や室外と室内の温度差を利用して換気する方法です。窓を開けて室内の空気を入れ替えるのも自然換気です。自然換気をうまく活用できる条件は、窓の開口部分が大きくて、天井近くの高い場所にあることです。 たとえば、冷たい空気は暖かい場所に向かって流れ込みます。この自然現象を利用して、床に近い窓から冷たい空気を取り込み、天井に近く高い窓から暖かい空気を逃します。そうすることで、温度差を利用した自然換気が行えるのです。
機械換気
機械換気は、モーターなどの電気を利用した動力で空気を循環させる換気方法です。ファンなどの送風機を使って換気するため機械換気と呼ばれます。キッチンやバスルーム、トイレなどに設置されている換気扇も機械換気の1つです。強制的に空気を排出できるので、換気量をしっかりと保持できることがメリットだと言えます。
3種類ある機械換気それぞれの特徴とは?

第1種換気
<特徴>給排気ともに換気ファンを使用
<メリット>熱交換システムを使えば外気温に影響されにくい
<デメリット>設置、メンテナンスなどに費用がかかる場合が多い
<メリット>熱交換システムを使えば外気温に影響されにくい
<デメリット>設置、メンテナンスなどに費用がかかる場合が多い
第2種換気
<特徴>給気は換気ファン、排気は排気口を使用
<メリット>常に新鮮な空気を取り入れて室内の空気圧を高め、外気が入りにくくなるため、菌や汚染物質が室内へ入るのを防ぎやすい
<デメリット>気密性の高い住宅以外だとメリットがない。外気温の影響を受けやすく、空調効率の低下が懸念される
<メリット>常に新鮮な空気を取り入れて室内の空気圧を高め、外気が入りにくくなるため、菌や汚染物質が室内へ入るのを防ぎやすい
<デメリット>気密性の高い住宅以外だとメリットがない。外気温の影響を受けやすく、空調効率の低下が懸念される
第3種換気
<特徴>給気は換気口、排気は排気ファンを使用
<メリット>設置する際のコストを抑えられる
<デメリット>外気温の影響を受けやすいため、空調効率の低下が懸念される
<メリット>設置する際のコストを抑えられる
<デメリット>外気温の影響を受けやすいため、空調効率の低下が懸念される
ちなみに戸建て住宅やマンションなどでよく使われる換気方法は第3種換気です。給気は各部屋に設置した給気口で行い、排気はバスルームやトイレなどの換気扇で行うのが一般的といえるでしょう。第3種換気は、室内に湿気が溜まりにくく、システムにかかる費用や電気代などのコストを抑えられます。しかし、給気口付近は外気温を感じやすくなってしまうのが難点です。冬に給気口から冷気が入るからと閉めてしまい、換気が不十分になっていた例もあるので注意しなければなりません。
機械換気の運転方法
機械換気は、さらに運転方法が2種類に分けられます。1つ目は、汚れた空気や臭気が発生しやすい箇所で常時稼働させる連続運転です。たとえば、リビングや寝室などに採用されます。2つ目が汚れた空気を一時的に換気する間欠運転です。間欠運転は、キッチンやトイレ、バスルームに採用されます。
機械換気の適用範囲にも種類がある

局所換気
局所換気とは、キッチンやトイレ、バスルームなど汚れた空気が溜まりやすい場所をピンポイントに換気することを言います。代表的な局所換気では、キッチンのレンジフードファンや浴室の換気扇が挙げられます。
全般換気
全般換気は、住宅を1つの空間として認識し、その全体を換気するシステムのことを言います。近年の高断熱、高気密住宅に採用される24時間換気システムが代表的な例と言えるでしょう。住宅内の空気を常にきれいな状態に保つシステムではありますが、局所換気が必要ないわけではなく、一般的に全般換気と局所換気はセットで採用される場合がほとんどです。
高性能住宅における温度・湿度・換気のバランス
高断熱・高気密と謳われる高性能住宅は、外気の影響を受けにくく快適な温度を維持する反面、その気密性の高さから常に空気を入れ替えることが重要です。しかし、換気の方法によっては部屋の暑さ寒さの要因になることも。快適な温度・湿度と空気の入れ替えを両立させるためには、熱効率の良い換気と、住宅の断熱性能を向上させる必要があるのです。
 >>>参考コラム:気密と換気の関係とは?効果的に換気をするためには気密性が重要!
>>>参考コラム:気密と換気の関係とは?効果的に換気をするためには気密性が重要!

香芝市周辺の気候は?季節の気候に合わせた換気をしよう
香芝市や葛城市、北葛城郡王寺町などがある奈良県の北部は、夏はむし暑く、冬は寒さが厳しい内陸性気候と言われています。そのため、窓を開閉することで冷暖房効率が下がる真夏と真冬は自然換気には向いていません。暑さ・寒さが原因で起こる熱中症、ヒートショックの健康被害も心配でしょう。人が快適に暮らすためには室内温度は大切です。そのためには外気を遮断、気密性を高める断熱で適温を保ち、換気システムで快適な湿度を維持するといいでしょう。つまり、気候に合わせて快適に暮らすには、断熱と換気が整った家づくりが重要なのです。
参考:奈良県地方気象台HP「奈良県の概要」
参考:奈良県地方気象台HP「奈良県の概要」
高性能住宅における換気システムのご相談はR+house香芝王寺へ!

>>香芝市周辺の気候に合ったR+houseの高断熱・高気密の性能についてはこちら